News
富山大学附属病院 吉田丈俊教授がシンガポールKKH「頭のかたち外来」を訪問
2025.09.22
赤ちゃんの頭のかたち健診とヘルメット治療の国際的な標準化・均てん化を通じた頭蓋健診と頭蓋矯正治療の質の担保のため、シンガポール最大の小児病院で実地視察・研修を実施。日本とシンガポールとの共同研究も決定
株式会社ジャパン・メディカル・カンパニー(東京都中央区、代表取締役CEO 大野秀晃、以下当社)は、当社提携先医療機関である富山大学附属病院 周産母子センター長/教授 吉田丈俊先生が、シンガポールのKK Women’s and Children’s Hospital(以下KKH)「頭のかたち外来(PlagioCentre)」を訪問し、外来を見学するとともに、現地の医師・義肢装具士・理学療法士に対し頭蓋健診とヘルメット治療に関する指導を行い、多職種チームと議論・意見交換を実施したこと、さらに第13回SiPPAC 2025に参加されたことをお知らせいたします。
本件は、赤ちゃんの「頭のかたち」に関する国際的な診療プロセスの標準化、評価指標の整備、共同研究推進の新たなステップを示すものです。
■ KKHにおける「赤ちゃんの頭のかたち外来」
シンガポール最大の女性・小児専門病院であるKKHでは、乳児における位置的頭蓋変形症の診療が年々増加しています。2022年の年間症例数は800件超でしたが、2024年には1,000件を超え、36%以上の増加となりました。
こうした医療ニーズの高まりを受けて、KKH内には乳児の頭のかたちに特化した専門外来「PlagioCentre(日本語訳: 頭のかたち外来)」が開設されました。
KKHのPlagioCentre(頭のかたち外来)のページ
PlagioCentreでは、小児科医、新生児科医、理学療法士、義肢装具士など多職種から成るチームが、適正な頭蓋健診、理学療法による変形予防、そしてヘルメット治療まで一気通貫して行っています。当社が開発・製造するクルムフィットが唯一のヘルメットとして、シンガポール政府の正式な入札を経て、外来開設時より現在も採用されております。
シンガポール初となる公的病院での頭のかたち外来は、1858年開院という約150年の歴史を持つKKHの伝統と革新に裏打ちされた、適正な頭蓋健診とヘルメット治療によって、治療効果の最大化が図られています。
専門外来の開設にあたっては、KKHで頭蓋矯正治療に携わる専門チーム(小児科医、理学療法士、義肢装具士)が2024年10月に来日、一般社団法人日本頭蓋健診治療研究会の行う研修を受講するとともに、一般社団法人日本ヘルメット治療評価認定機構の認定医療機関を訪問しています。
来日時の研修を通じ、KKHの専門チームは日本式の頭蓋健診と頭蓋矯正治療についての学びを深め、2024年11月からシンガポールでの臨床にあたっています。
日本・シンガポール間の緊密なコミュニケーションにより、日本発の乳児の頭蓋変形に対する取り組みが世界的に見ても標準的な治療として拡大しています。
関連プレスリリース:日本式の「赤ちゃんの頭のかたち」矯正治療(ヘルメット治療)が海外へ進出/ジャパン・メディカル・カンパニー社製のヘルメットを用いた頭蓋矯正治療がシンガポールで開始
【参考サイト】
一般社団法人日本頭蓋健診治療研究会
一般社団法人日本ヘルメット治療評価認定機構
■ 訪問の意義
吉田教授は2022年より富山大学附属病院で「頭のかたち外来」を主導してきた経験をもとに、KKHの外来を実際に見学。その後、同院の頭のかたち外来チームに対し、位置的頭蓋変形(斜頭症・絶壁など)と病的頭蓋変形(頭蓋縫合早期癒合症)の鑑別やヘルメット治療の適応判断について講義と指導を行いました。
富山大学附属病院の診療の現場で行われているプロセスを取り上げ、低線量スズCTを用いた非侵襲的頭蓋健診の活用、患者・家族への説明方法、フォローアップ体制の整備といったテーマについて、KKHの小児科・脳神経外科・看護師・リハビリスタッフなど多職種チームと活発な議論を交わしました。
吉田教授による具体的症例の共有は、KKHの臨床チームからも高い評価を得ており、今後の相互研修や共同研究につながる礎となりました。


吉田教授は併せて13th SiPPAC 2025にも参加し、周産期・新生児・小児医療の幅広い演題を通じて、アジア圏の診療課題や医療提供体制の違いについて理解を深めました。
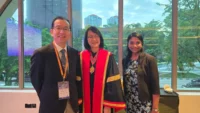

■ 学会参加による相互理解の深化
 ▼KKH頭のかたち外来チームとの面談、講義の目的と感想
▼KKH頭のかたち外来チームとの面談、講義の目的と感想
KKHの頭の形外来を担当している新生児科のKavitha Sothirasan先生から位置的斜頭症と早期癒合症との鑑別について教えてほしいと言われて講義してきました。また、私もシンガポールで行われている頭の形外来について興味があったので見学してきました。
ヘルメット装着開始月齢が6.5か月、ヘルメット装着期間が2.85か月(すべて平均値)と日本より開始が遅く装着期間も短いながらCVAIの改善が9.58=>4.44と素晴らしい結果でした。一方、早期癒合症は1年間で症例がなく、日本の当院(注:富山大学附属病院)とは大きな違いでした。この斜頭症のヘルメット治療の効果や早期癒合症の発症率に関して、今後シンガポールと日本で共同研究することになりました。これからもお互いの知見をシェアして頭の形に悩むお子さんと親御さんに貢献していきたいと感じました。
▼13th SiPPAC 2025参加の所感
初めてシンガポールでの学会に参加させていただきましたが、まず参加者の80%以上が女性であることに驚きました。日本でも小児科は女性が多い科の一つですが、感覚的にはシンガポールでは周りはほぼ女性という感じでした。また発表内容の半分以上が新生児関連でした。発表の内容は日本と似た部分が多かったのですが、シンガポールでは心の病を抱えたお子さんが多いことに驚きました。熱帯地方なのでもっと感染症の話題が多いかなと予想していましたが、シンガポールは超近代国家なのでそういう話題は全くありませんでした。また、医療保険制度もないため、医療内容がご家族の経済状態によって変わってくることも日本とは異なり新鮮な知見でした。同じアジア諸国として、まずはお互いを知ることが大切だと実感した学会でした。
【参考】富山大学附属病院と当社間における共同研究の取り組み
富山大学附属病院とジャパン・メディカル・カンパニーが「日本の小児における頭蓋変形の疫学調査」についての共同研究を開始
■ 国際的な医療連携の促進
当社は、医療機器やサービス提供にとどまらず、一般社団法人日本ヘルメット治療評価認定機構の方針に基づき「適正な頭蓋健診と適正な頭蓋矯正治療」の国内外の均てん化を推進しています。
https://jcqht.org/
一般社団法人日本ヘルメット治療評価認定機構では下記3つの要件を満たす医療機関を認定対象としています。
SNSや一部メディアで「手軽な美容矯正」と誤解されがちな頭蓋矯正ヘルメット治療に対し、当社は医療的根拠と認定機構の方針に基づいた正しい情報発信と国際連携、そして研修会やセミナーの運営・支援を通じ、乳児と家族が安心できる診療体制の確立を支援してまいります。
今後も当社は、富山大学附属病院やKKHをはじめとする提携医療機関と協力し、国際共同研究・専門外来視察・相互研修を継続的に実施。頭蓋健診と頭蓋矯正治療の質の向上と均てん化を通じ、グローバルな医療の発展に寄与してまいります。
株式会社ジャパン・メディカル・カンパニー(東京都中央区、代表取締役CEO 大野秀晃、以下当社)は、当社提携先医療機関である富山大学附属病院 周産母子センター長/教授 吉田丈俊先生が、シンガポールのKK Women’s and Children’s Hospital(以下KKH)「頭のかたち外来(PlagioCentre)」を訪問し、外来を見学するとともに、現地の医師・義肢装具士・理学療法士に対し頭蓋健診とヘルメット治療に関する指導を行い、多職種チームと議論・意見交換を実施したこと、さらに第13回SiPPAC 2025に参加されたことをお知らせいたします。
本件は、赤ちゃんの「頭のかたち」に関する国際的な診療プロセスの標準化、評価指標の整備、共同研究推進の新たなステップを示すものです。
■ KKHにおける「赤ちゃんの頭のかたち外来」
シンガポール最大の女性・小児専門病院であるKKHでは、乳児における位置的頭蓋変形症の診療が年々増加しています。2022年の年間症例数は800件超でしたが、2024年には1,000件を超え、36%以上の増加となりました。
こうした医療ニーズの高まりを受けて、KKH内には乳児の頭のかたちに特化した専門外来「PlagioCentre(日本語訳: 頭のかたち外来)」が開設されました。
KKHのPlagioCentre(頭のかたち外来)のページ
PlagioCentreでは、小児科医、新生児科医、理学療法士、義肢装具士など多職種から成るチームが、適正な頭蓋健診、理学療法による変形予防、そしてヘルメット治療まで一気通貫して行っています。当社が開発・製造するクルムフィットが唯一のヘルメットとして、シンガポール政府の正式な入札を経て、外来開設時より現在も採用されております。
シンガポール初となる公的病院での頭のかたち外来は、1858年開院という約150年の歴史を持つKKHの伝統と革新に裏打ちされた、適正な頭蓋健診とヘルメット治療によって、治療効果の最大化が図られています。
専門外来の開設にあたっては、KKHで頭蓋矯正治療に携わる専門チーム(小児科医、理学療法士、義肢装具士)が2024年10月に来日、一般社団法人日本頭蓋健診治療研究会の行う研修を受講するとともに、一般社団法人日本ヘルメット治療評価認定機構の認定医療機関を訪問しています。
来日時の研修を通じ、KKHの専門チームは日本式の頭蓋健診と頭蓋矯正治療についての学びを深め、2024年11月からシンガポールでの臨床にあたっています。
日本・シンガポール間の緊密なコミュニケーションにより、日本発の乳児の頭蓋変形に対する取り組みが世界的に見ても標準的な治療として拡大しています。
関連プレスリリース:日本式の「赤ちゃんの頭のかたち」矯正治療(ヘルメット治療)が海外へ進出/ジャパン・メディカル・カンパニー社製のヘルメットを用いた頭蓋矯正治療がシンガポールで開始
【参考サイト】
一般社団法人日本頭蓋健診治療研究会
一般社団法人日本ヘルメット治療評価認定機構
■ 訪問の意義
吉田教授は2022年より富山大学附属病院で「頭のかたち外来」を主導してきた経験をもとに、KKHの外来を実際に見学。その後、同院の頭のかたち外来チームに対し、位置的頭蓋変形(斜頭症・絶壁など)と病的頭蓋変形(頭蓋縫合早期癒合症)の鑑別やヘルメット治療の適応判断について講義と指導を行いました。
富山大学附属病院の診療の現場で行われているプロセスを取り上げ、低線量スズCTを用いた非侵襲的頭蓋健診の活用、患者・家族への説明方法、フォローアップ体制の整備といったテーマについて、KKHの小児科・脳神経外科・看護師・リハビリスタッフなど多職種チームと活発な議論を交わしました。
吉田教授による具体的症例の共有は、KKHの臨床チームからも高い評価を得ており、今後の相互研修や共同研究につながる礎となりました。

吉田先生(写真中央)とKKH頭のかたち外来の新生児科医Kavitha Sothirasan先生(左から3人目)、義肢装具士・理学療法士等の外来スタッフ

吉田先生による講義(富山大学附属病院における低線量スズCTを用いた非侵襲的頭蓋健診の取り組み、患者・家族への説明方法やフォローアップ体制についての説明等)
■ 学会参加による相互理解の深化吉田教授は併せて13th SiPPAC 2025にも参加し、周産期・新生児・小児医療の幅広い演題を通じて、アジア圏の診療課題や医療提供体制の違いについて理解を深めました。
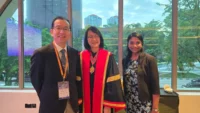
写真中央:Chua Mei Chien教授(KKH医学部門副チェアマン/KKH新生児科部長/KKHヒューマンミルクバンク所長/シンガポール国立大学小児科アカデミック・クリニカルプログラム 臨床准教授)

学会会場にて関係者と記念撮影
学会での参加者同士の交流により、日本とシンガポールの臨床現場の相違や共通課題に対する理解が深まり、日星間の補完的な協力関係がさらに具体化しました。■ 学会参加による相互理解の深化
 ▼KKH頭のかたち外来チームとの面談、講義の目的と感想
▼KKH頭のかたち外来チームとの面談、講義の目的と感想KKHの頭の形外来を担当している新生児科のKavitha Sothirasan先生から位置的斜頭症と早期癒合症との鑑別について教えてほしいと言われて講義してきました。また、私もシンガポールで行われている頭の形外来について興味があったので見学してきました。
ヘルメット装着開始月齢が6.5か月、ヘルメット装着期間が2.85か月(すべて平均値)と日本より開始が遅く装着期間も短いながらCVAIの改善が9.58=>4.44と素晴らしい結果でした。一方、早期癒合症は1年間で症例がなく、日本の当院(注:富山大学附属病院)とは大きな違いでした。この斜頭症のヘルメット治療の効果や早期癒合症の発症率に関して、今後シンガポールと日本で共同研究することになりました。これからもお互いの知見をシェアして頭の形に悩むお子さんと親御さんに貢献していきたいと感じました。
▼13th SiPPAC 2025参加の所感
初めてシンガポールでの学会に参加させていただきましたが、まず参加者の80%以上が女性であることに驚きました。日本でも小児科は女性が多い科の一つですが、感覚的にはシンガポールでは周りはほぼ女性という感じでした。また発表内容の半分以上が新生児関連でした。発表の内容は日本と似た部分が多かったのですが、シンガポールでは心の病を抱えたお子さんが多いことに驚きました。熱帯地方なのでもっと感染症の話題が多いかなと予想していましたが、シンガポールは超近代国家なのでそういう話題は全くありませんでした。また、医療保険制度もないため、医療内容がご家族の経済状態によって変わってくることも日本とは異なり新鮮な知見でした。同じアジア諸国として、まずはお互いを知ることが大切だと実感した学会でした。
【参考】富山大学附属病院と当社間における共同研究の取り組み
富山大学附属病院とジャパン・メディカル・カンパニーが「日本の小児における頭蓋変形の疫学調査」についての共同研究を開始
■ 国際的な医療連携の促進
当社は、医療機器やサービス提供にとどまらず、一般社団法人日本ヘルメット治療評価認定機構の方針に基づき「適正な頭蓋健診と適正な頭蓋矯正治療」の国内外の均てん化を推進しています。
https://jcqht.org/
一般社団法人日本ヘルメット治療評価認定機構では下記3つの要件を満たす医療機関を認定対象としています。
- 機構主催の医師・スタッフ・関連メーカー対象の研修と認定試験への合格
- 先行施設での実地見学研修の受講
- 鑑別診断に必要なエックス線等の診断機器の保有
SNSや一部メディアで「手軽な美容矯正」と誤解されがちな頭蓋矯正ヘルメット治療に対し、当社は医療的根拠と認定機構の方針に基づいた正しい情報発信と国際連携、そして研修会やセミナーの運営・支援を通じ、乳児と家族が安心できる診療体制の確立を支援してまいります。
今後も当社は、富山大学附属病院やKKHをはじめとする提携医療機関と協力し、国際共同研究・専門外来視察・相互研修を継続的に実施。頭蓋健診と頭蓋矯正治療の質の向上と均てん化を通じ、グローバルな医療の発展に寄与してまいります。

